
Lesson for Smile Project
- あなたのレッスン受講が、笑顔につながる -
レッスン1回で1円相当の食事支援を、セブ島の子どもたちへ。
あなたの「学び」が誰かの「生きる力」になります。
現在の支援実績
-
-
参加人数
- 1,164 人
-
-
-
レッスン数
- 26,699 回
-
-
-
食事の数
-
68
※食
※1食あたり約390円
-

Lesson for Smile Projectとは?
あなたが普段通りに受けているQQEnglish・QQジュニア・QQキッズのレッスンが、フィリピン・セブ島に暮らす子どもたちへの食事支援に繋がります。ご参加いただいた方のレッスン1回ごとに、1円相当の支援を、CampusTopグループが責任をもって現地の子どもたちへお届けします。
英語を学ぶあなたの取り組みが、世界の誰かの未来を照らす。
「学び」を通じてつながる、あたたかな支援の輪に、あなたも参加してみませんか?
※CampusTopグループとはグローバルに展開する教育グループで、日本では「株式会社QQ English」として事業を展開しています。

WHYなぜフィリピンの子どもたちへ?
CampusTopグループの英会話教師たちは、全員がフィリピン出身。私たちの英語学習を支えてくれている「仲間」でもある彼らの祖国に“少しでも恩返しをしたい”それがこのプロジェクトの出発点です。
フィリピンは現在、発展途上国として様々な課題を抱えています。 一方、かつての日本も、戦後に多くの国々の支援を受けて復興を遂げました。
今度は私たちが、「教育」という形で、未来への支援を届けていきたいと思っています。
PHILIPPINES
REALITYフィリピンの貧困地区の実態
-
笑顔の裏にある、厳しい現実
- フィリピンでは、都市のすぐ近くにも貧困地域が広がっており、多くの子どもたちや家族が厳しい生活を送っています。彼らは狭く壊れやすい家に住み、電気や水道も十分に利用できない環境で暮らしています。学校に通えず働かざるを得ない子どもや、1日1回の食事さえままならない家庭も少なくありません。
-


-
栄養不足と生活習慣病のリスク
- その「1日1回の食事」も、米やインスタント麺などの炭水化物に偏りがちです。野菜やたんぱく質を摂取する機会が極端に少なく、多くの子どもたちが栄養不足に陥っています。このような偏った食生活は、血糖値の急激な変動を引き起こし、集中力の低下や体調不良につながるだけでなく、将来的に糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めることもあります。 それでも、そのような困難な環境の中、子どもたちは元気に笑い、将来の夢を語ってくれます。小さな希望を大切にし、前向きに日々を生きています。
-


私たちにできること、そして未来へ
今回、私たちはそんな子どもたちへ向けた「食事支援」を行います。
栄養のある食事を届けることで、彼らの身体を守り、学びに集中できる環境を整えたいと考えています。
この支援の積み重ねが、子どもたちの未来を支える大きな一歩となると信じています。
私たちにできる支援は、小さなものに思えるかもしれません。
しかし、その「小さな力」が、子どもたちの安心、健康、学び、そして未来へとつながっていくと信じています。
この現実を一人でも多くの方に知っていただき、支援の輪が広がっていくことを心から願っています。
CampusTopグループの
これまでの取り組み
ACTION
QQEnglishの課外授業
- 私たちCampusTopグループは、これまでも現地のNGO団体と連携し、 貧困地区にて食事配膳や生活支援などの活動を続けてきました。
子どもたちの「ありがとう」の声や、あふれる笑顔が、私たちの大きな原動力です。 -

-
2020年
-
コロナ禍でも支援を止めない――
先生たちと築いた“もう一つの挑戦”2020年、セブ島も新型コロナウイルスによるパンデミックの影響でロックダウンされ、語学留学の受け入れは全面停止に。QQEnglishにとっても、学校運営の半分を支えていた「セブ島留学」が突然ゼロになるという、未曾有の事態が訪れました。 それでも私たちは、「生徒さんの学びを止めない」「先生たちの雇用を守る」この2つを軸に、全力で新しい体制を築いていきました。 授業はすべてオンラインに切り替え、経費削減のために校舎の一部を手放すなど大胆な判断も行いました。 そして何よりも心強かったのは、先生たちの存在です。 フィリピンでは厳格なロックダウンにより、一度校舎に入ると家族と何年も会えない覚悟が必要でした。 それでも先生たちは「海外に出稼ぎに行くつもりで」と言って泊まり込み、 安定したネット環境と徹底したトレーニングのもと、どこよりも質の高い授業を届けてくれました。その努力の積み重ねにより、オンライン英会話は3倍以上の規模に成長し、「退会率が業界平均の半分」と言われるほどの満足度を実現することができました。
もっと詳しく見る -


-
-
2021年
-
台風(オデット)――
困難に直面しても、止まらない挑戦さらに2021年末には、フィリピンを襲ったスーパー台風オデットにより、セブ島が壊滅的な被害を受けました。 中心気圧915hPa・最大瞬間風速75mの台風が直撃し、通信・水道・電気すべてが停止。 それでも私たちは、備蓄や自家発電を活用して、スタッフ・教師・その家族を含めた600人の命と生活を守りながら、授業再開に向けて即日行動を開始しました。 実際に被災の5日後には、ITパーク校で全体の8割の授業提供を再開。 通信も通じない中、手紙とバイクで連携を取りながら、学校内に避難所とキッチンを設け、食料と水を分け合い、前を向いて進みました。 設備が壊れても、インフラが止まっても、何より大切なのは“人”。 この経験が、私たちの教育と支援の根底にある「人への思い」を、より強く支える原動力になっています。
もっと詳しく見る -


-
あなたも仲間に加わりませんか?
レッスン受講が支援につながる!
プロジェクト申し込みをしてくださった方は、レッスン1回ごとに1円相当の支援をすることができます。
(QQEnglish・QQジュニア・QQキッズのレッスン対象)
集まった支援がフィリピンの子どもたちの食事支援に充てられます。
学びが、誰かの笑顔につながる。そんなやさしいプロジェクトです。
プロジェクト参加方法
-

-
参加は簡単!登録するだけ。
以下の「プロジェクトに参加する」ボタンより登録申し込みをお願いします。レッスン数をカウントして、皆様のレッスン受講数×1円相当のご飯をCampusTopグループがセブ島の貧困地区で子ども達に届けます!(頻度:月に1回を予定)
プロジェクトに参加する
Lesson for Smile Projectは
SDGsに賛同します
私たちの取り組みは、持続可能な未来を目指す国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」の理念同しています。
その一環として、教育機会の拡大や子どもたちの笑顔につながる活動を推進しています。
特に以下の目標に貢献しています。

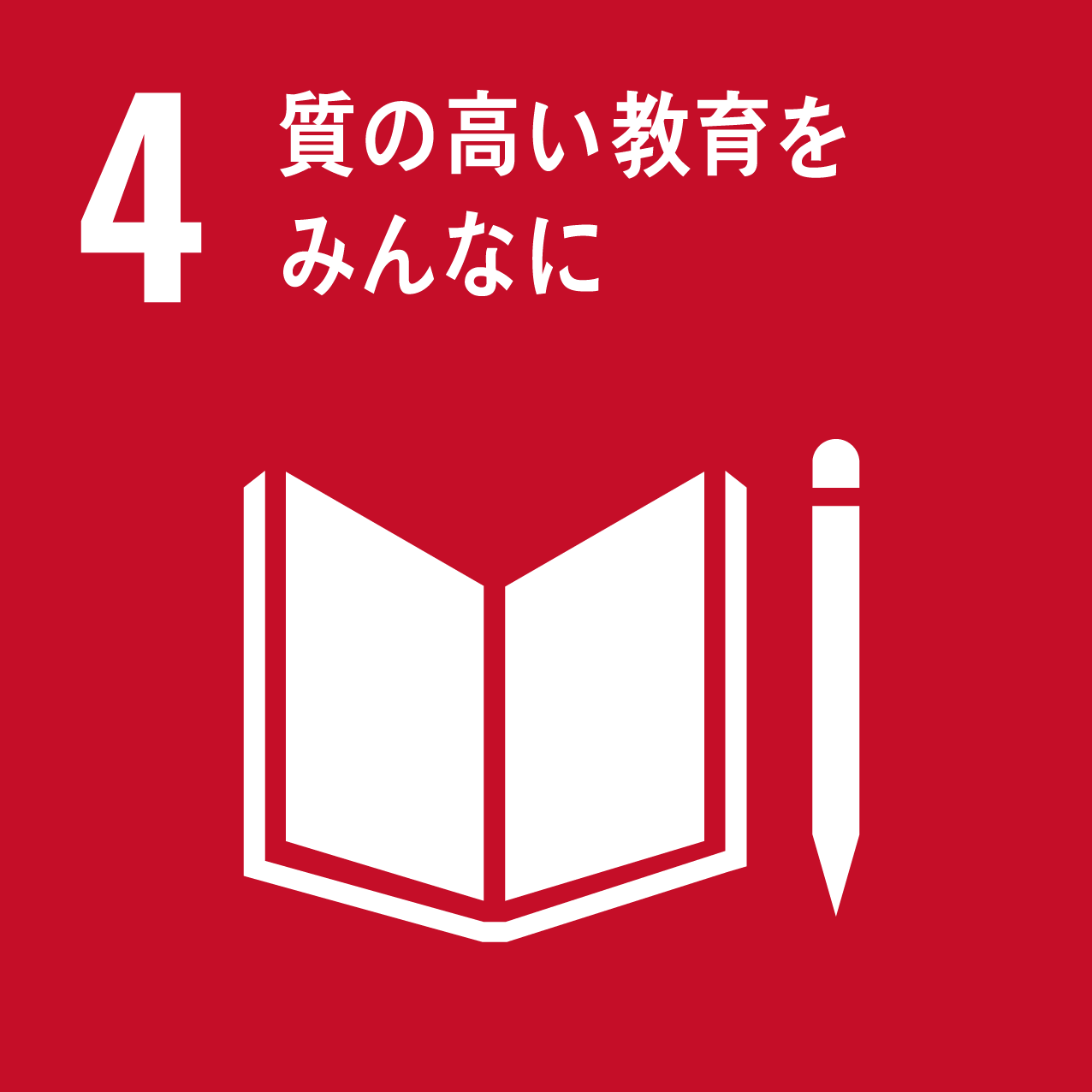
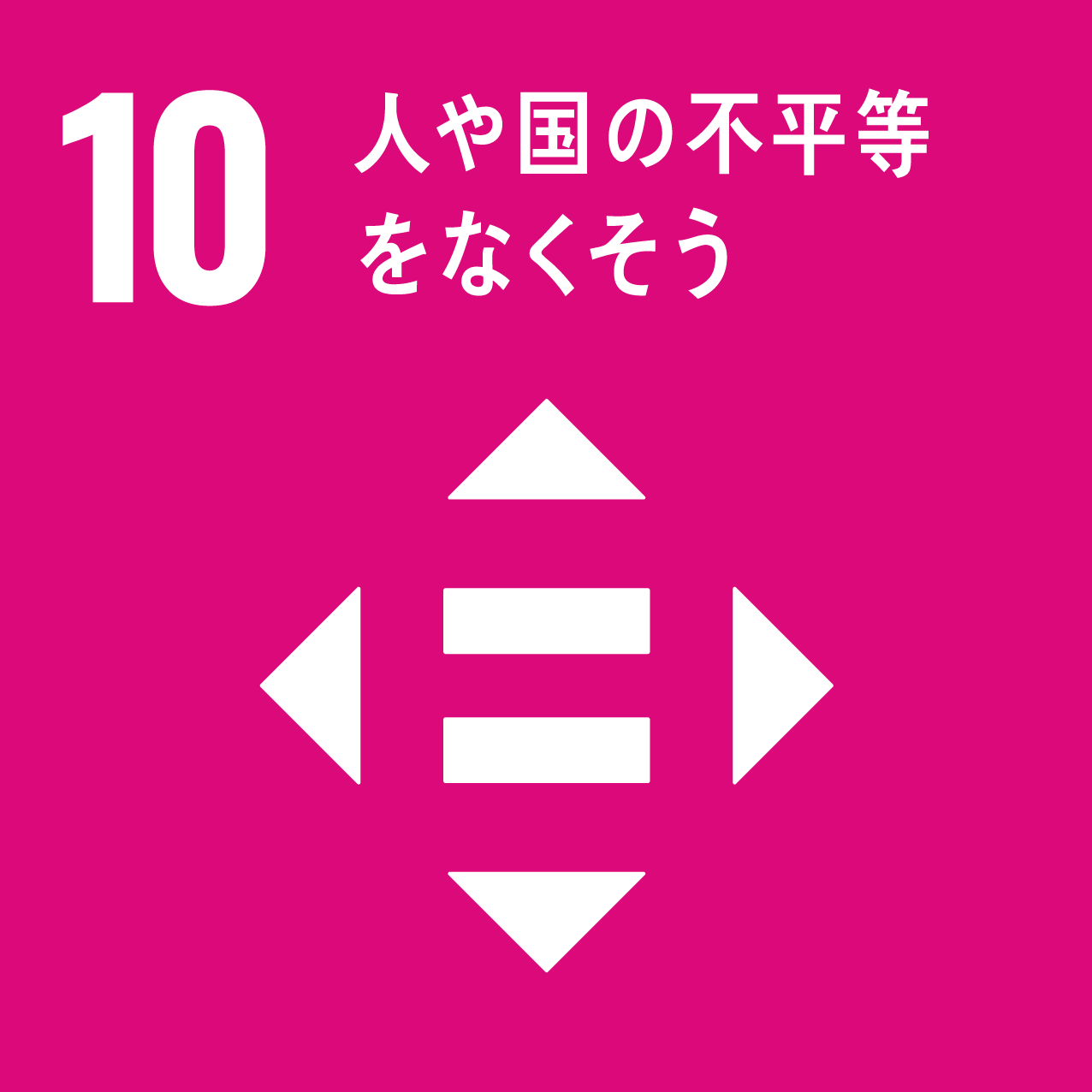
※SDGsロゴおよびアイコンは、国連の公式ガイドラインに基づき使用しています。
CampusTopグループとは
-
-
- 全員正社員のフィリピン人教師による、最高品質のオンライン英会話。日常会話からビジネス・TOEIC対策までオールマイティに対応しています。通常の4倍速で英語が身につくと言われる大人気の学習法「カランメソッド」の正式認定校です。
-
-
-
- QQEnglishの品質はそのままに、中学生に特化したカリキュラムをご用意しております。入試対策やテスト対策、留学準備など中学生に合わせたサービスを提供しています。
-
-
-
- 3歳~12歳までを対象とした、子ども専門のオンライン英会話です。多彩なカリキュラムの中から年齢やレベルに合うレッスンを選んで受講することができます。
-
-
-
- QQEnglishはフィリピン初の日系語学学校として全ての教師を正社員雇用し、質の高い学習体験を提供しています。最高の立地にある校舎と宿泊施設で海外留学を経験できます。
-
-
-
- 未就学児から中学生を対象の完全オーダーメイド型のオンライン早期英語習得プログラムです。専属日本人コーチがつき、目標達成や学習の習慣化により高くコミットできます。
-
-
-
- 「カランメソッド」を採用し、 短期間での“発話量最大化”を実現するプログラムです。ビジネスシーンなど、より高い英語力を求める方へのコーチングサービスです。
-
VISION企業理念
-
ミッション
- To be the Gateway to the world!― 世界へのゲートウェイとなる
- CampusTopグループのミッションは、世界へとつながる「通路」であり、「出入り口」となることです。たとえ今は英語がたどたどしくても、私たちのサービスを通じて学ぶことで、英会話力を身につけ、世界のどこへ行っても円滑なコミュニケーションができるようになります。
まさに、世界へ通じる扉となることこそが、私たちに課せられた使命だと考えています。
CampusTopグループは、生徒の皆さまが当校での英語学習を通して「世界で活躍できる人材」となり、「新たな可能性を切り拓く」ことを目指し、全力でサポートしてまいります。
-
ビジョン
- To be the most recognized company that creates opportunities for everyone.― より多くの人に、人生を変える機会を提供する会社になる
- このビジョンを掲げた背景には、生徒の皆さまの英語力向上に貢献するだけでなく、CampusTopグループで働く教師やスタッフと共に成長できる学びの場を築きたいという想いがあります。CampusTopグループは、フィリピン・セブ島に語学学校を構え、すべての教師を正社員として雇用しています。安定した職場環境を提供することで、貧困や雇用不足といった社会課題の解決にも、小さな一歩を積み重ねていきたいと考えています。
2009年の創業以来、教師の質の向上に力を注ぎ、すべての教師が国際的な英語教授法「TESOL」の研修を修了しています。こうした取り組みが評価され、当校はフィリピン政府から正式な語学学校として認定を受けました。質の高いレッスンを通じて、生徒の皆さまの英語力を高めると同時に、教師自身のキャリアと誇りを育むこと——それがCampusTopグループの目指す姿です。学ぶ人と教える人の未来に寄り添いながら、これからも歩みを進めてまいります。














